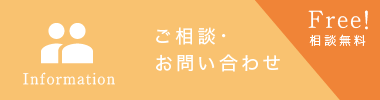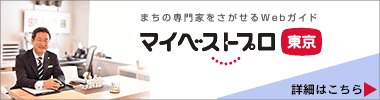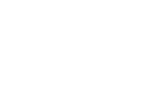先日のニュースで、目の見えない生涯を持つ子供の将来を悲観して母親が息子を絞殺するという悲しいニュースがありました。「新聞がたまっている」と近隣住民が近くの交番に通報した事から駆けつけた所轄の警察署員が、民家1階の和室で男性の遺体を発見。民家にいた母親が遺体は自分の息子で、首を絞めて殺害したと認めたため、殺人容疑で緊急逮捕したというものです。
この事件に限らず、障がいを持つ子供を抱えて将来に対する不安を抱えている親御さんは多いのではないでしょうか。その場合、親がまだ元気なうちは良いのですが、親世代も段々年を重ねて行きます。そうした中で、親の気持ちとして、もし、自分が先に死んでしまったら、この子はどうなってしまうのだろうか・・・という気持ちが募って行くのは当然だと思います。しかし、このニュースのように将来を悲観して子供を殺してしまうというのはとても悲しく、また、最悪の結末です。
では、何か良い手だては無かったのでしょうか?例えば、多少なりとも財産があれば、遺言でその財産の全てを子供に相続させれば良いのではと思います。しかし、親の気持ちとしては、誰かに騙されてしまうのではないか?自分亡き後、自分で財産の管理がちゃんと出来るのだろうか?といった不安は残ります。では、誰かに自分の財産を遺贈する代わりに、子供の行く末をお願いできないだろうか?という事も考えられます。いわゆる負担付き遺贈と言われる方法です。この方法では、お願いした相手がちゃんと希望通り子供の面倒を見てくれれば良いのですが、必ず見てくれるという保証もありません。では、成年後見の制度を活用してはどうでしょうか?残念ながら、成年後見制度は知的障がいや精神障がいの人を守る制度で、このケースのような目が見えない子供、つまり身体障がい者は制度の対象外ということになります。しかし、実際にはこの事例のように子供が身体障がい、あるいは、引きこもり、浪費癖、などで親の気持ちとしては自分亡き後どうやってこの子は生きて行くのだろうという心配されているケースは数多くあるのではないかと思います。そんな時に活用して頂きたいのが「家族信託」です。家族信託とは平成19年に信託法が改正施行されて信託銀行などが行っている商事信託に加えて運用できるようになった「家族型の民事信託」の事です。日本ではこれまで信託といえば、信託銀行などが運用する商事信託の事を指していました。
そもそも「信託」という概念の始まりは中世ヨーロッパで十字軍に従軍する兵士が自分の信頼する友人などに自らの財産を託して、不在の間、自分の代わりに妻や子を守って欲しいと依頼した事に端を発すると言われています。正に「信じて託す」これが「信託」という概念の根幹にあります。ですから、この家族信託という新しい制度は極めてその信託の始まりの頃の概念に近いものではないかと思います。
また、この家族信託の制度を活用すると、親子などの親族間で財産を託して、将来の相続(争族)や認知症などのリスクに備えたり、遺言では出来ない数世代に渡る家産継承が可能になったり、自分亡き後、成年後見制度の対象にならない障がいなどを持つ配偶者や子、引きこもりや浪費癖の子の生活を支えたり、家族同然の愛するペットを守る仕組みを自分が元気なうちに構築することが出来ます。非常に画期的な制度ですので、これから将来の相続問題や自らの認知症リスクなどに対する対策を考えている方にとっては強い味方になる選択肢の一つだと思います。
相談事例1(事業継承) http://www.j-ssa.net/q11/
相談事例2(ペット信託)http://www.j-ssa.net/q06/
相談事例3(家産継承)http://www.j-ssa.net/q05/